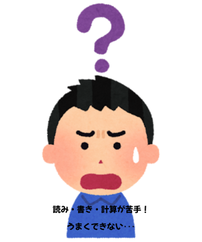
◆今回は、学習に問題がある、限局性学習症(SLD)の説明をします。
全般的な知能が正常範囲(知的能力障害と区別される)にあり、視覚(視力)や聴覚(聴力)には障害がありません。
学習環境や本人の意欲にも問題がないにも関わらず「話す」「聞く」「読む」「書く」「計算する」「推理(推論)する」ことなど、特定の領域だけがうまくできないという状態です。
これは、文字の読み書きや数字の理解に関わる脳(中枢神経)の働きが、十分に発達していないことによると考えられています(特異的発達障害)。
◆限局性学習症(SLD)の主症状
→読字の困難(ディスレクシア)【字を読むことに困難が生じる状態】
- 形の似た字を間違える。
- どこで区切って読めば良いか分からない。
- 困難な状況としては、読み飛ばしや読み替えによる間違いが多い。
- 文字は読めても、単語や文として読むことが難しい。
- 内容を理解することが難しい。
- 文字を一つ一つ拾わないと読めない(逐次読みをする)。
- 読んでいるところを指で押さえたり、枠で囲わないと読めない。
- 文末などを適当に変えて読んでしまう。
→書字の困難(ディスグラフィア)【文字や文章などを手書きすることなどに困難が生じる状態】
- 鏡文字を書いてしまう(空間認知に問題があると考えられる)。
- 漢字を部分的に間違う。
- 単語を正確に書くことが難しい。
- 文字(板書)を書き写すのに時間がかかる。
- 主語・述語などの文法構造の理解が難しい。
- 助詞の誤用が多い。
- 文章(作文)を書くことが難しい。
- 「ょ」「っ」など、特殊音節を抜かして書いてしまう。
- 「め」と「ぬ」など、形が似ている文字を間違えて書いてしまう。
- 書くべき欄やマス目からはみ出て書いてしまう。
- 不自然と思える句読点の打ち方をする。
- 単純な文章しか書けない。
→算数・推論の困難(ディスカリキュリア)【数学の能力を獲得することに困難がある状態】
- 数字の概念が理解できない。
- 簡単な計算ができない
- 5番目と5つの違いが理解できない。
- 数字を読んだり、描いたりすることに困難が見られる。
- 筆算が難しい。
- 計算での繰り上がり、繰り下がりが理解できない。
- アナログ時計の時刻が読めない。
- 文章題を解くことに困難がある。
- 表やグラフを含む問題を解くことに困難がある。
- 図形を理解したり、図形を描いたりすることが困難である。
- 九九を覚えられていない。
- 九九を暗記しても、計算に応用できない。
◆限局性学習症(SLD)支援におけるポイント
※何に困っているかが重要です。
(1)読字困難の場合
- 子どもが読んだ後、教える側(保護者、教師、その他の大人など)がゆっくり、正確に読むことが大切です。
- ページを読むごとに、場面を把握しているかを確かめると良いでしょう。
- 文の少ない本人の好きな絵本の交代読みをしてあげてください。
- 可能な限り、文章の読み上げをすることも効果的です。
- 大きな文字で書かれた文章を、指でなぞりながら読む練習をします。
(2)書字困難の場合
- 初期には、なぞり書き練習を繰り返し行います。
- 間違う度、叱らず、できるまで正しいものを見せると良いでしょう。
- 文字の始点を示し、曲がるところで声をかけて、間違わないように練習を繰り返します。
- 大きなマス目のノートを使うことも大切です。
- 学校では、カメラ板書・パソコン(タブレットなど)の使用許可など、保障的な支援をお願いすると良いです。
(3)算数・推論困難の場合
- 絵を使って数字を視覚化すると良いでしょう。
- 子どもの得意な力(図や言葉で理解する力)を使えるようにすると効果的です。
- 数の即時把握遊び、比較遊びおよび数の分解遊びをすることも大切です。
- 文章題では文章を分け、絵に表してください。
- 文章を図式化することも効果的です。
(4)まとめ
- つまずきは「克服する」ものではなく、子どもにあった方法を見つけることで解消するものです。
- 学習が定着しているかどうかを確認し、もし定着していない場合は、別のやり方を検討する必要があります。
- 子どもに合った学習方法を見つけることが大切です。
- 子どもが課題を間違えた時、「ここができていないね。」ではなく、「ここまでできているね!」と声かけをしてあげると自信がつきます。
- 他者と比較せずに、自己肯定感を高めるアプローチを中心に置くよう、心掛けてあげましょう。
※上記の内容は、下記の文献を参考にして作成しました。
- 野村総一郎・樋口輝彦ら「標準精神医学」医学書院, 2015.
